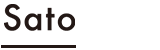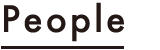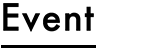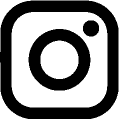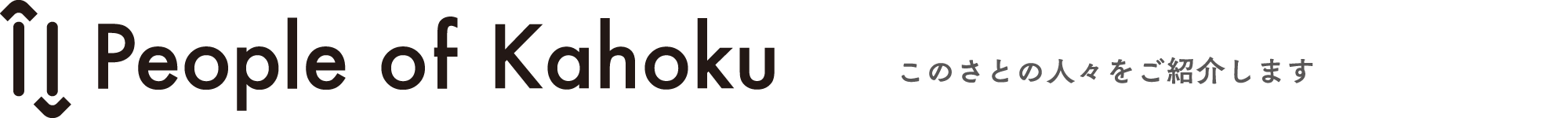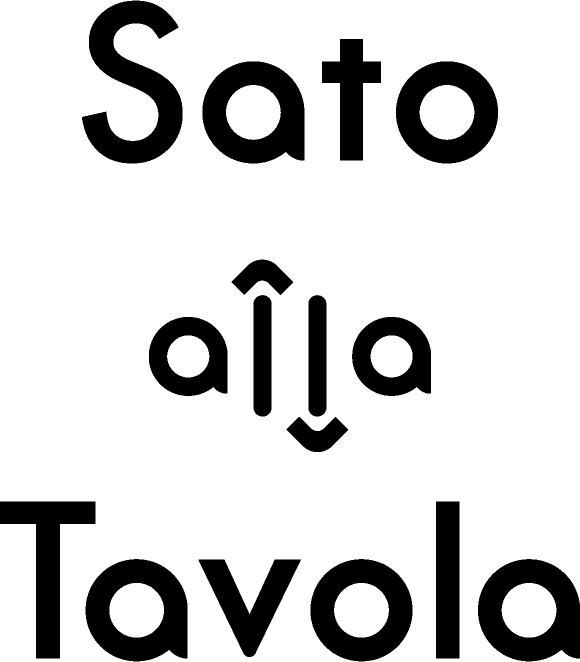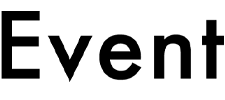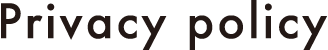宝石のような果実たち
さとタボラチームが巡るフルーツの旅路
2024.12.06


宝石のような果実たち
さとタボラチームが巡るフルーツの旅路
2024.12.06
さとタボラ取材チームは、11月初旬2日間にかけて河北町を取材しました。たくさんのフルーツ農家の方を訪問し、逐一その出来栄えとおいしさに唸るシェフとチームメンバーたち。山形といえば、さくらんぼや桃にはじまるフルーツ。中でも河北町はフルーツ栽培に絶好の場所なのだとか。その理由を探るべく、まずはラ・フランス農家を訪問しました。

(「安部ファーム」の安部敏明さん。)
ラ・フランス/安部ファーム
「河北町は最上川と寒河江川に挟まれた肥沃な土壌に位置し、水も豊かで盆地の気候なので、フルーツが育ちやすく、おいしくなりやすいんです。自分も若い頃から親の農園を継ぐつもりでいました」と語るのは、「安部ファーム」の安部敏明さん。山形盆地は梅雨時期に雨が少ないため果実が割れにくく綺麗に育ち、昼夜の寒暖差により糖を蓄えて甘くなります。さらに冬場の安定した積雪量で蓄積された水分は、春先に作物が元気に芽吹くのを促してくれるのです。

(安部ファームのリンゴ園からの眺め。)
「フルーツではラ・フランスが一番好き」という安部さん。糖度や品質を保つためにきめ細やかな管理をされています。収穫後すぐ冷蔵庫に入れて10日から2週間予冷し、そこから18〜20度ほどの温かいところに移して追熟させます。果物は7度以下で呼吸が止まり、休眠するため、予冷の際は7度を超えない温度管理が重要。お客様の手元に届く頃に最もおいしい状態になるようシステマチックにケアされている果物たち。

(予冷庫で予冷中のラ・フランスをチェックする安部さん。)
畑に伺うと、ラ・フランスの木は収穫を終えたばかり。シェフが地に落ちた果実を一つ受け取って、その香りにうっとりです。

(さとタボラの池田シェフ。ラ・フランスの香りでたちまちお料理が思い浮かんだ…はず。)
その横に黄玉や富士などのリンゴの木が美しく茂っていました。リンゴの収穫のタイミングは、気候がぐっと寒くなり霜が降りてから。寒さによって、果実の中の澱粉が糖に変わるのだそうです。しかし「今年はまだ収穫できませんね」。例年は11月の前半には霜が降りてくるのに対し、今年、11月時点では、一向にその気配なし。寒さが来ないと赤みも薄いため、「今年は雪の中もぐはめになるかもしれません」と安部さん。去年は、低気圧の異常気象で4000kgもの果実が落ちてしまったということも。年々新たな厳しさもありながらも、やはり河北町のフルーツのおいしさを届けたい、と工夫を凝らして精力的に励む安部ファームさんです。

(「雪の中で収穫しないといけないかも…」と言いつつも、やる気みなぎる安部さん。)
手搾りジュースとアーモンド/クダモノラクエン
翌日取材チームが向かったのは、「クダモノラクエン」さん。数々のフルーツ栽培を手がけると同時に、手搾りにこだわったフルーツジュースも製造販売しています。1L瓶には、果実が7~8個ほど入っています。水も何も加えない文字通りの100%ジュースは、まごころと栄養満点。手搾りだからこそ生まれる透明感や旨みがあるのだそうです。

(「クダモノラクエン」の手搾りジュース製造の風景。)
ジュース作りの工程を説明しながら、「めっちゃアナログでしょ」と笑う、オーナーの生稲洋平さん。搾りたての湯気が立ち上るラ・フランスジュースを一口飲んださとタボラのシェフたちは、「めっちゃうまい」と驚き表情。生稲さんのラ・フランスジュースは、りんごよりも希少。旬の時期に作って、すぐに売り切れてしまう人気商品です。

(アナログへのこだわりを朗らかに語る生稲さん。)
ジュースを搾り終えると、生稲さんは不思議な光景を見せてくださいました。照明器具のようなものの上に、ピカーっと光り輝くリンゴ。この器具は、「蜜ライト」と言って、リンゴの蜜入り状況を確認するためのものなのだそうです。蜜が入っているとよく光るのだそうで、そのような果実は、いわゆる「蜜入りリンゴ」の名をうたうことができます。

(蜜ライトに照らされた蜜入りリンゴ。)
「でもね」と生稲さんは言います。蜜入りというと市場では価値が上がるけれど、蜜が入っていなくても糖度は高くなるのです。蜜入りは完熟し切っている状態なので蜜がいっぱい入っているほど日持ちしないというのも事実。蜜が入っていないものでも、おいしいものはたくさん。そうした畑の恵みを余すところなく、ジュースに加工したり、料理の食材として提供したり。生稲さんは果実の活かし方をよく知っている、とシェフの間でも評判の農家さんなのです。

(蜜入りであってもなくても、リンゴ一つ一つに、それぞれに良さがある。)
生稲さんは、各種フルーツの他にナッツの栽培も手がけています。6年前に「かほくナッツ研究会」を発足し、町内の同志を募って国産ナッツに挑戦。現在栽培しているナッツは3種類。マルコナとダベイというアーモンド2種と、ヘーゼルナッツです。マルコナは大粒で食べ応えがあり、ダベイはまさに杏仁豆腐の香り。ヘーゼルナッツは成木にも時間がかかり、今年ようやく収穫できた嬉しさは「言葉にならない」と生稲さん。ただ、まだ今は歩留が悪いため、商談会などで見せるのみ。これからの成長に期待です。

(今年のアーモンドの収穫量は73kg!)
「工場で殻を割るほどの量がないので、一つ一つハンマーで手で割ることになるけど…」という生稲さんの言葉に、さとタボラのシェフはすかさず「全然割ります!ハンマーで!」と答え、仕入れをさせていただきました。シェフが視察中、Instagramのストーリーズに河北町のナッツについてアップしたところ、料理人仲間から「いいね!どこのもの?」とさっそく反響が。国産ナッツが熱い今、河北町のナッツ生産もいよいよ勢いを増していきそうです。

(ハンマーでアーモンドを割る様子。中の生アーモンドは香り豊か。)
ぶどうとワイン/はじまり農園う〜の
最後に訪れたのは、「はじまり農園う〜の」の宇野さんの畑。「食べてみる?」と特別にもいでいただいたシャインマスカットとクイーンニナの甘さと水々しさに、畑の中で目を丸くするメンバーたちでした。

(気前よくシャインマスカットを振る舞ってくださる宇野さん。いただくのは、畑を見学に来た人の特権です。)
河北町は2021年からワインの製造も行っています。その原料であるデラウェアなどのブドウの生産を一手に引き受けているのが宇野さん。実も皮も余すところなく使う「醸し」で、野生酵母のみで発酵する「かほくワイン」。風土、土壌、収穫する年々の気候や畑の状態など、さまざまな要素でワインの味が決まります。「ワインづくりは毎年新たな発見がある」と宇野さん。

(地域おこし協力隊でやってきた醸造士の滝口さん。)
例年のデラウェアに加え、今年初収穫したナイアガラで醸造した「かほくワイン2024」は、トロピカルフルーツの白桃のような香りが際立ち、 口当たりは柔らかくドライな仕上がり。 「今年の宇野さんのブドウは酵母がとても元気でした」と語るのは、醸造士の滝口恵子さん。「国内外さまざまな葡萄畑を見てきましたが、宇野さんの畑は河北町の中でも高台の方にあり、土壌の水捌けが良いので、ブドウの実がとても綺麗ですね」。宇野さんはじめ、町の人々の思いの詰まった「かほくワイン」。ぜひ今年の味をご賞味ください。

(「かほくワイン」デラウエア ナイアガラ2024VT)
畑で垣間見た、河北町の自然風土とつくり手たちの情熱。そのクオリティーの高さに驚き、感動すら覚えたかほくフルーツの旅路でした。