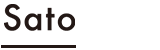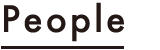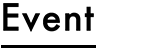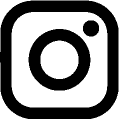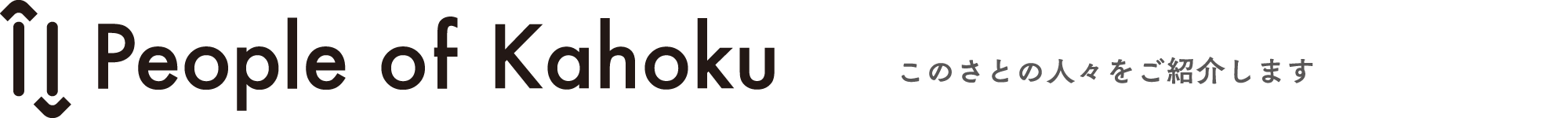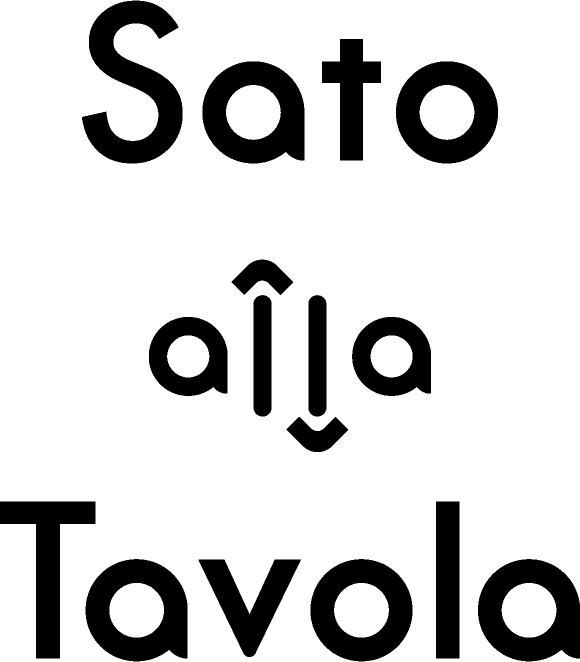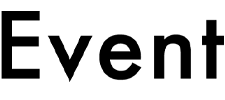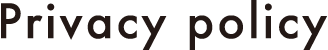奇跡のものづくりのまち
イタリア野菜から始まったものづくりの循環
2024.12.06


奇跡のものづくりのまち
イタリア野菜から始まったものづくりの循環
2024.12.06
古より人々のくらしを支えてきた、山形の母なる最上川。その川辺に沿うように位置する河北町はかつて、最上川舟運による紅花の集散地として栄えた場所でした。紅花は、江戸時代から明治初期にかけて重要な染料でした。紅花を通じた繁栄は、華やかな上方文化を河北町にもたらし、今も町が盛り上がるお祭り、『谷地どんがまつり』の始まりにもなっています。古くから、新たな文化やモノ・コトを受け入れ、発展してきた河北町。実は、この東西最大約8kmの小さな町は今、知れば知るほど興味深い数々のモノづくりが勢いを増しているのです。

そんな河北町のモノづくりの「今」を語るのに、「イタリア野菜」の存在は欠かせません。皆さんは、河北町が日本全国でも有数のイタリア野菜の産地であることをご存知でしょうか。都内の高級レストランを含む約200軒もの店舗に、年間60品目もの河北町産イタリア野菜が出荷されています。その品質には定評があり、「辛味」「風味」といったイタリアンに欠かせない、野菜本来の特徴が際立っていて、本場イタリア産にも引けを取らないと評判。個人で店を経営するシェフから町へ直接の発注も後を絶ちません。

(イタリア野菜の代表、ラディッキオタルディーボ。とある冬、町内の畑にて。)
河北町がイタリア野菜をつくり始めたきっかけは、ほんの10年ほど前のこと。新鮮な国産のイタリア野菜を求めて、町内出身のシェフが自宅の台所で自家栽培を試みていたことがすべての始まりでした。河北町と似たイタリアの寒冷な地域が原産地であるイタリア野菜を、町の冬の産業にできないか。シェフの小さな試みと、町を盛り上げたいと熱い想いを持つ何人かの目に留まり、町ぐるみのプロジェクトへと発展していったのです。そうして発足されたのが、「旧かほくイタリア野菜研究会>※(通称「イタ研」)」16人の自称「イタリア野菜オタク」のメンバーで、試行錯誤が始まりました。
(※現在は「かほくらし生産組合」に合併)

(イタリア野菜も手がける農家の太田さん。「ちょっと大きくなりすぎた」という太田さんが手に持っているのは、立派なローザビアンカ)
当初は町内にイタリア野菜の栽培方法を知る人間は皆無!Youtubeや農学雑誌を読み漁っては試行錯誤の連続。炬燵で発芽させ、収穫までこぎつけたはいいものの、喜びも束の間、一体どこを食べたらおいしいのか分からなかったという笑い話もあるほど。藁をもつかむ思いで有名シェフや料理研究家にコンタクトをとると、皆関心を寄せてくれ、多くの人が河北町を訪れるようになり、知識の輪が広がっていきました。「イタ研」メンバーは、栽培の傍ら東京のイタリア料理店にも足繁く通っては勉強の日々。同時に、レストラン一軒また一軒と、徐々に販路を拡大していったそうです。実際に畑で土をさわり作物を育てているつくり手自らが、出荷された後、素材が使われる現場まで赴くという、惜しまない努力と熱心な研究が、河北町を名産地へと成長させていったのでしょう。

(町内のつくり手たちは度々集まって、最近の作物の出来栄えや新しい品種についてなど語り合う。)
2019年、「イタ研」メンバーの念願が叶い、原産地であるトレヴィーゾ地方を視察。現地に赴いて、河北町の方が冬の寒さがずっと厳しいことを体感し、その寒暖差に耐えて天然の冷蔵庫となる雪下で冬を越した野菜は糖度がぐっと増すということにも気づきます。原産地と異なる気候が、河北町独自のおいしさにつながるヒントとなり、有名料理店を唸らせる品質を確立し、こうして「かほくイタリア野菜」ブランドができあがったのです。

(成長したタルディーボ。ここから暗いところに移して水耕栽培を行うと、クリスマスにぴったりな赤く鮮やかな色になる。)
そんな町をあげてのモノづくりの動きは、同じように「町を盛り上げたい」と志を同じくする生産者の間に横のつながりを芽生えさせました。町内の異業種がつながり始め、産業が循環し始めたのです。酒粕をイタリア野菜の肥料として提供する老舗、「和田酒造」。B級品のビーツが畑の隅に余っているのを見て、ビーツカレーを商品化する精肉店「サンミート吉田」さん。イタリア野菜の捨てられてしまう部分を利用して、麹調味料を開発する糀屋「矢ノ目糀屋」さん。

(「サンミート吉田」の吉田圭佑さんと事業を手伝う妹さん。イタリア野菜がゴロゴロと入ったベジタブルカレーは、動物性油脂を一切使用せず、野菜の旨みを最大限に活かしている。)
そして、いつしかその循環の輪は「6次産業化」に向かい、農に携わるつくり手たちが売り方までを見据えて切磋琢磨し始めます。良い酒米の作り方を酒造と共に学ぶ勉強会や、町産のぶどう100%の「かほくワイン」の醸造。耕作放棄地を活用して国産ナッツを栽培しようと発足された「かほくナッツ研究会」。ちなみに、町内の凄腕の洋菓子店「パティスリー・デ・ジョワ」が作る、町産ナッツや酒粕を使った絶品スイーツも大変な評判です。

(パティスリー・デ・ジョワの武田大介さん。代々の和菓子屋を洋菓子店に転身させた敏腕の4代目。町内の食材やフルーツを使ったツイーツで町を盛り上げようとするアイデアマン。)
河北町の面白い食文化はまだまだたくさんあります。山形のB級グルメとして有名な「冷たい肉そば」の発祥地でもあり、町内には十数件ものお蕎麦屋さんが軒を連ねます。町民は冬でも「冷ったいの(冷たいの)」を好んで食べるそうです。河北町にお越しの際は、ぜひご賞味を!

(冷たい肉そば。地元の人の発音は、「つったいにくそば」。)
「農」を源流として、畜産、養鶏、製乳、造酒、発酵業、加工業、染め物、工芸、スリッパまで、様々な生業がひしめき合う河北町。熱い情熱を持ったつくり手たちが集い、支え合う、心地良い循環のある町。河北町の食とその背後のストーリーは、心身が元気になる栄養がたっぷりなのです。