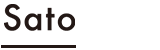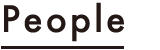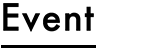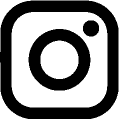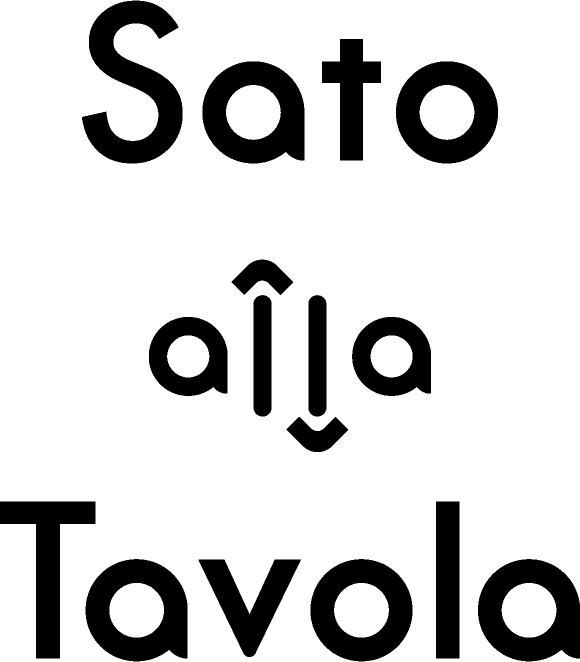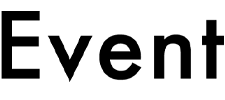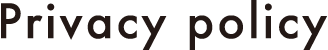海に呼ばれて、天草へ
熊本県天草視察ノート①
2025.08.13

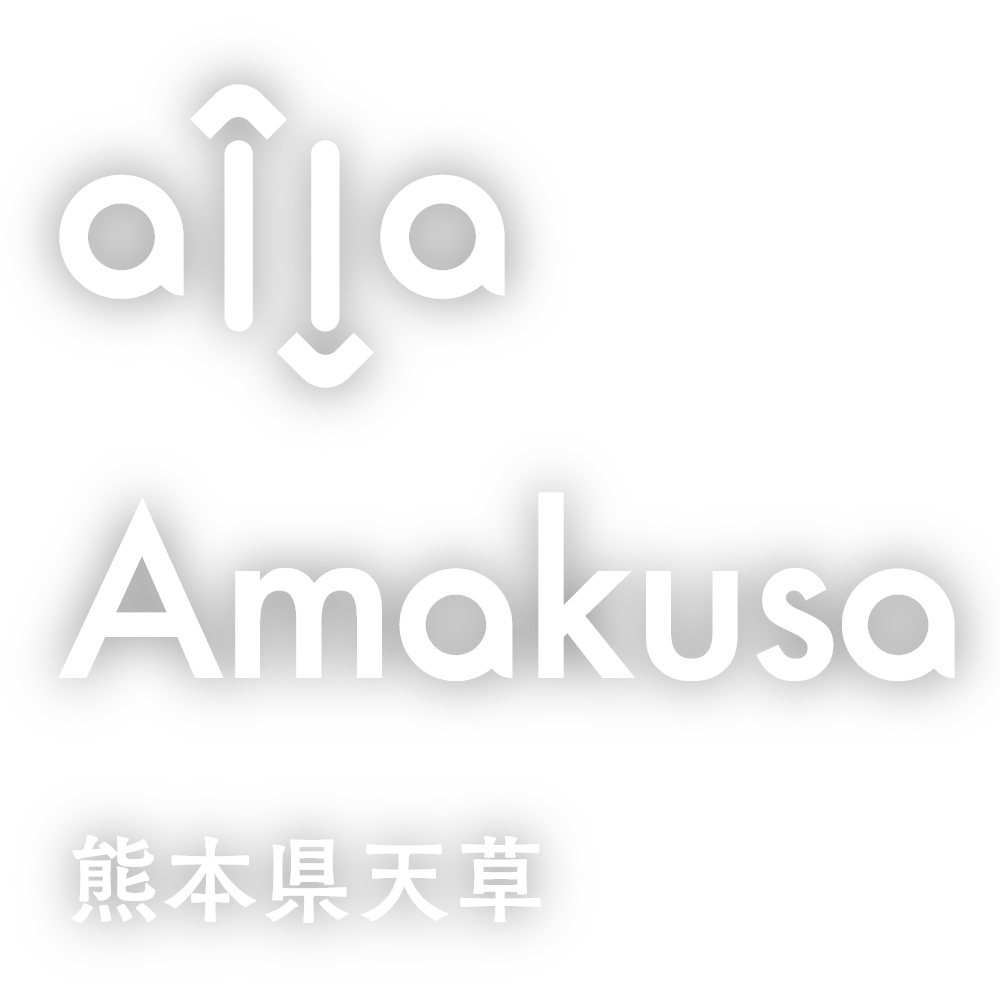
海に呼ばれて、天草へ
熊本県天草視察ノート①
2025.08.13
2025年6月30日、さとタボラ視察チームは飛行機で熊本空港に降り立ちました。そこからレンタカーに飛び乗り、島にかかる「天草五橋」を渡り抜け、天草の下島に上陸。この日は雲ひとつない晴天で気温は33度、湿気が高く海からはもやが立ちのぼっていました。

※写真提供:合同会社シーベジタブル
到着したのは「シーベジタブル」の生産拠点。
「シーベジタブル」は“海藻は海の底で育つもの“という常識をひっくり返し、種苗の研究にはじまり、海藻の陸上栽培と海面栽培に取り組む会社です。

案内役の生産マネージャー・丸山拓人さんは、教育業界から海藻生産の世界に飛び込んだ、異色の経歴の持ち主。前職の退職日に、かつてからの知人でもある代表・友廣さんと再会したことがきっかけで入社したといいます。「最初はアルバイトのつもりでしたが、今年で7年目です」と穏やかに笑います。この天草の拠点は、丸山さんをはじめとするシーベジタブルのメンバーが、水槽設計や撹拌機械の開発、細かな備品なども、改良を重ねながら手作りして立ち上げたといいます。

シーベジタブルで陸上栽培をしているのりのひとつに「すじ青のり」があります。香りがきわめて強く “海藻界の香りの王様”と呼ばれるのりです。シーベジタブルが手掛ける「すじ青のり」はひときわ香りが高いため、料理人の間では“海のトリュフ”とも称されているとか。

乾燥前のすじ青のりをいただきました。名前の通りすじのような細い青のりです。一本一本は糸のように繊細なのに、香りがよく海藻の旨みも濃密です。乾燥させるとさらに香りと旨みが際立つそうで、お米だけでなくチーズなどの乳製品や油とも相性が良いそうです。

どうして、これほど香り高いすじ青のりが育つのでしょうか。理由はいくつかありますが、安定栽培ができるような種苗の研究開発、そして青のりの生育状況に合わせた生育管理などがあげられます。成長の段階に合わせて常に良い状態で青のりが育つことができるため、芳醇な香りで栄養豊富なすじ青のりになるのだそうです。

海面栽培で育てた「とさかのり」と「みりん」もいただきました。どちらも赤い海藻ですが、食感はまったくの別物でした。肉厚でコリコリとした歯応えのとさかのりと、じゅるりと崩れるような食感のみりん。田邉シェフは複数の食感から何やらヒントを得たようです。

チームは車を走らせ、天草下島の北部に位置する五和町鬼池に向かいました。ここには日本最西端のホップ畑をもつブルワリー「AMAKUSA SONAR BEER」があります。ビール醸造所に併設されたタップルームのドアを開けると、レゲエの音楽が心地よく流れてきました。この日、出迎えてくれたのはブルワーの角麻紀子さんと、アシスタントブルワーの菱沼哲さんです。ふたりとも出身は九州ではありませんが、天草の海に魅せられそれぞれ移住してきたそうです。角さんは2年目、菱沼さんは半年前からこの地で暮らしています。

店内には、天草をはじめ熊本県産のフルーツをふんだんに使ったクラフトビールが並びました。中でも特徴的なのが、「フルーツスムージーサワー」と呼ばれるスムージータイプのビールです。口当たりがとろっとしていて、フルーツの甘味も強くでる、従来のビールの枠を超えた新しい味わいを提供しています。「もったりしてるからサーバーから注ぐのは結構難しいよ。俺ベトナムでタコス屋やってた時は、ビールを注ぐのは1回も失敗しなかったの。でもこれを注いでいると下手くそに見えちゃう」と菱沼さん。

同ブルワリーでは、10種以上のホップを自社畑で栽培し、毎年9月に収穫しています。「ホップは寒冷地で育つので、天草では育ちにくいです。株分けをしながら少しずつ増やしています」と角さんが教えてくれました。

こうして収穫されたホップと、地元の無農薬パール柑を使用してつくられたのが「White Pearl(ホワイトパール)」です。パール柑は天草を代表する柑橘類で、名前の由来は真珠の名産地である天草にちなんでいるのだとか。分厚い皮を一つひとつ手で剥き、皮と果肉をジューサーにかけて使用しています。柑橘の豊かな香りと、料理の味を邪魔しないすっきりとした後味が特徴で、食事とのペアリングにも適しています。チームメンバーの目が「これだ!」と言わんばかりに輝きました。

その後「AMAKUSA SONAR BEER」を後にしたチームは、須賀無田(すがむた)海岸の「天草塩の会」の吉川恵さんの元を訪れます。そこでは、吉川さんが34年にわたり、昔ながらの製法で塩を作り続けていました。

1991年にパートナーの松本明生さん(享年70歳)とともに、「理想の塩作りの地」を求めて天草に移住。条件は「川も民家もない(生活排水が流れていない)、海水がきれいで広い場所であること」だったといいます。

塩作りで大事なことは「どれだけゆっくり丁寧に作れるか」だと吉川さんは話します。

まずは海水を蒸発させて濃度を高めた「かん水」を作ります。海から直に海水をホースで汲み上げ、ポンプで木組みのやぐらの上から黒いネットへと掛け流します。海水はネットに染み込み太陽と風にさらされて、水分のみが徐々に蒸発していきます。滴り落ちた海水はやぐらの下を流れ、再びタンクへと導かれます。この工程を何度も繰り返すことで、塩分濃度約3%の海水から約15%のかん水へと濃縮されていきます。

やぐらの下に目をやると、白と黒の石がまばらに散りばめられていました。「松本が『水の流れをゆっくりにした方が、日がよく当たるだろう』と、あえて水を蛇行させるように不規則に石を並べたんです。ただ松本は囲碁が好きだったので、白と黒を並べてみたかっただけかもしれませんね」と吉川さんは笑います。

結晶の粒が細かい「煎熬塩(せんごうえん)」は、このかん水を炊き上げて作られます。季節や天候に左右されにくく、安定した品質の塩ができるのが特徴です。

薪をくべて鉄窯に火を入れ、時々アクをとり、日々新しいかん水を加えながら蒸発を促していきます。週に1回のペースで行われる炊き上げ作業では16時間かけて火をくべていきます。かん水の塩分濃度が27度を超えると結晶化が始まります。

塩が結晶化した後の液体が、にがりです。この塩とにがりを木の樽に移し、なじませながら寝かせていきます。その後にがりと塩分を分離させたら完成です。

煎熬塩を舐めると、しょっぱいだけでなく丸みがあり、
複雑で奥行きのある味わいでした。聞けば鉄窯を使用するため、鉄分が入っていることも関係しているのだそうです。田邉シェフは特ににがりにも注目したようで、「メニュー開発用にどうにか少し持ち帰りたい」と吉川さんに相談していました。

天草の海は「美しい」「おいしい」だけではなく、人の心を動かし、足を運ばせるだけの力を持っている──そんなふうに感じられた、ものづくりの現場でした。明日はそんな天草で生まれ育った、けれどまったく異なる個性をもつ2組の生産者さんを訪ねます。
──ところで。夕食を食べようと街の飲食店の扉を開けたら、なぜか「AMAKUSA SONAR BEER」の菱沼さんがいて「待ってたよ」と私たちにコップを掲げてくれたのは、ここだけの話です。