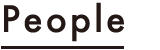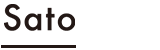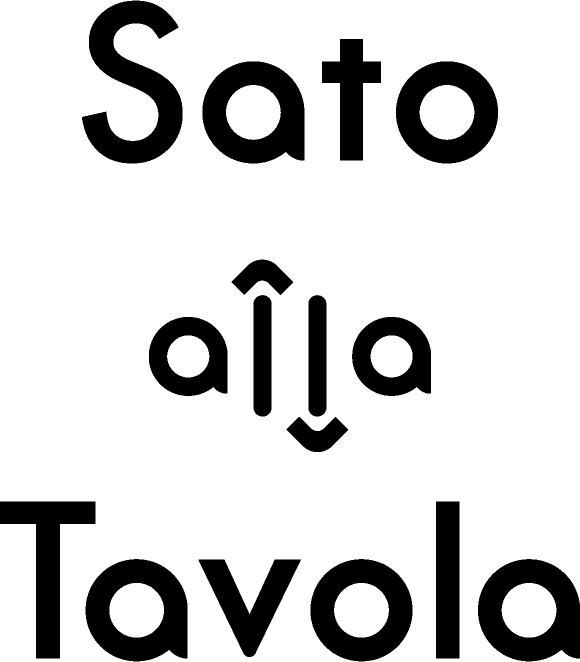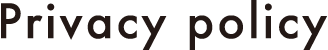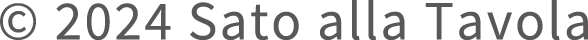「北限の茶所」生産現場へ 茨城県大子町視察ノート(1)
2025.04.23


「北限の茶所」生産現場へ 茨城県大子町視察ノート(1)
2025.04.23
2024年4月10日、さとタボラ視察チームは、朝イチの東北新幹線に乗り込み、「那須塩原」駅に降り立ちました。天気は晴天。春の陽気の中にも少し肌寒い空気に、関東の北端に近づいたことを実感したメンバーたち。そこから東南の方向へ車を走らせて約45分。栃木との県境を越え、茨城県に入ってすぐの場所が、大子町の左貫(さぬき)という集落です。

重なり合う山々の隙間を埋めるように広がる民家と畑。車を停め、高台に向かって集落を歩いていくと、野菜畑に混じって、茶畑もちらほら見えてきました。この地域では、隣の家との敷地の境にお茶の苗を植え、自家用の茶葉を栽培しているところも多いそうです。茨城県を南北に走る久慈川の上流域を奥久慈(おくくじ)と言いますが、このエリアで、昔から生産されてきたのが奥久慈茶。坂を上りきると、整然と広がる茶畑に到着。視界が更に遠くまで開けました。チームが最初にお会いしたつくり手は、髙見園さん(上下写真中の赤い屋根がオーナーの家。周辺の茶園が髙見園)。実に約500年ほど続くと言われる奥久慈茶の名家です。

長い歴史を持つ奥久慈茶
チームを出迎えてくれたのは、髙見園のオーナー、髙信(たかのぶ)修一さん。大子町の生まれで、子供の頃からこの地域にお住まい。先祖代々続く茶園を切り盛りしています。その昔、僧により宇治などから家庭薬としてお茶が持ち込まれたことが、この地域のお茶栽培の始まり。そしてその最初は、大永年間に左貫地区内にあった西福寺の僧によると言い伝えられています。髙見園さんの茶園の近くにも、雲巌寺(うんがんじ)という美しいお寺があります。高信さん曰く、髙見園さんのお茶はそのお寺の住職さんから譲り受けたものではないか、とのこと。時間軸の壮大なお話の始まりに、チーム一同は興味津々。聞くと、髙信さんという苗字は平安時代にまで遡るそう。その時代の征夷大将軍として有名な、坂上田村麻呂が蝦夷征伐に行く際に、この辺りの農民をお供させ、見張り役にした人間を高信と名付けたことが由来なのだそうです。

大子町はお茶の栽培に適した地?
長い間お茶がつくられ続けてきたということは、この地域はお茶栽培に向いているということでしょうか?「いえいえ、ギリギリのところでやっている」から、大変なことも多いという高信さん。そもそもお茶は暖かい地域のもの。奥久慈は日本全国で見ても、茶葉の産地としては北限なのだそうです。大子町は山に囲まれた内陸の盆地で、かつ県内で最も標高が高いエリア。山の斜面から冷たい空気が流れ込むことで、夜は気温は下がりやすく、1日の中でも寒暖差が激しいのが特徴です。

お邪魔した当日は4月の中旬でしたが、この日の寒暖差は約20度。昼間は薄手の長袖1枚でも寒くない気温でしたが、朝方は氷点下まで冷え込み、この茶畑にも霜が真っ白に降りたそうです。雪や霜はお茶にとって天敵。今までは霜除けの布をかけたりして人の手でケアしてきましたが、最近になって茶畑全体をカバーできる大型の扇風機が建てられ、一役買っているそう。整然と列になっているのが茶畑の定番のイメージですが、高信さん曰く、綺麗な列になるのは、お茶が元気に育っている証拠。また、古い芽が残っていると、新茶を摘む時に雑味になり品質が落ちてしまうため、丁寧に丸く刈り込むのはとても大切なのだそうです。

人の手がかけられていることを知った上で改めて眺める茶木の列。その間を歩いて行くと、靴底に当たる土が驚くほどにふわふわであることにも気づきました。これは、町内の酪農家などから出た堆肥を畑に還元するための取り組みとして、大子町堆肥センターから堆肥を購入して畑に撒いているのだそうです。列の間を手押し車を引いて、歩いて撒くという手のかけよう。しかしこの一手間をかけることで、土の質がぐっと良くなるそうです。産地として北限に挑みながら、こんなにも手間ひまをかけてつくられ続け、全国的にも好まれ続けてきた奥久慈茶には、どのような特徴があるのでしょうか?
寒暖差に耐え抜いてできる“肉厚”の茶葉
奥久慈茶は、「寒いところで育っているだけに、味にコクがある」と髙信さんは言います。髙見園さんの茶葉は、何煎もおいしく飲めると評判なのだそう。その秘密は、茶葉の厚み。寒暖差に耐えて、葉はどんどん肉厚に成長するのだそうです。例えば静岡茶の浅蒸しの場合は20秒程度で蒸し終わるのに対して、奥久慈茶は葉が厚く、蒸気が浸透するのに3倍ほどの時間を要します。しかし、葉が硬いというわけではなく、あくまで分厚い。地元では新芽を天ぷらにするそうです。肉厚な香り高い茶葉の天ぷらのお味を想像して、チーム一同はつばをゴクリ。すると、「まぁ、お茶飲んでみっけ?」と髙信さんがカフェに招き入れてくださいました!

髙見カフェの絶品エスプレッソ
最初に奥さまのみどりさんが振る舞ってくださったのは、小さなカップに入った、濃い緑色の「煎茶エスプレッソ」。一口飲むと、驚くほどの甘味と旨味が口の中に溢れます。奥さま曰く、「茶葉はいつもより多め、お湯は低めの温度で、二段階から三段階に分けて、ゆっくりと注ぐこと」がコツ。茶葉の様子をよく見て、ふやけてきたら茶葉より少し多めのお湯を注ぐというのを繰り返すと、ゆっくりと茶葉が開き、甘味と旨味が引き出されるそうです。後味にほんのりとした苦味と、フレッシュな茶葉の香り。こんなにおいしいお茶が自宅でも飲めたら。チーム一同そのおいしさと、お茶がもたらすほっこり豊かな時間に感動しました。

髙見園さんではオーナー制度を導入しており、毎年オーナーの茶摘みイベントを開催。摘んだ新茶は持ち帰って自宅で釜炒り茶にするもよし、天ぷらにしてこの時期にしか味わえないお味を楽しむよし。チームメンバーも、オーナー制度に興味津々です。最近では手作業の茶摘みの風景はあまり見られなくなりましたが、その時期にはたくさんのオーナーたちが茶畑に入り、芽を摘みます。昔は大人数で歌を歌いながら一斉に行ったという茶摘みですが、新しい形でその風景を継承しているのは素敵なことですね。

オーナー制度の案内を握り締めて髙見園さんを後にし、とん鈴さんの奥久慈しゃもの親子丼のお昼をいただいてから、お次は奥久慈水穂村へ。そこには、若き米農家のエースがいるという噂です。
視察ノート(2)に続く