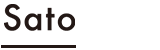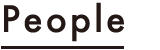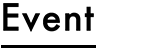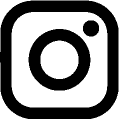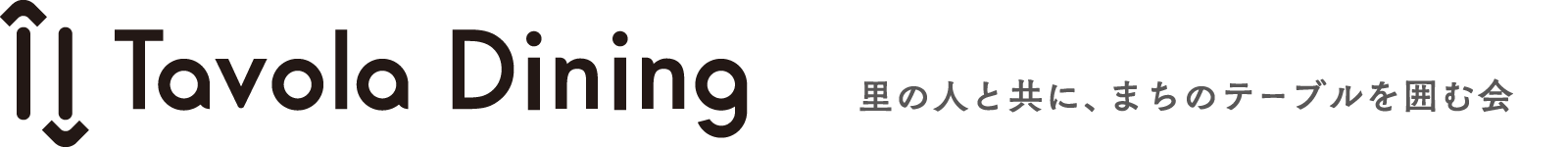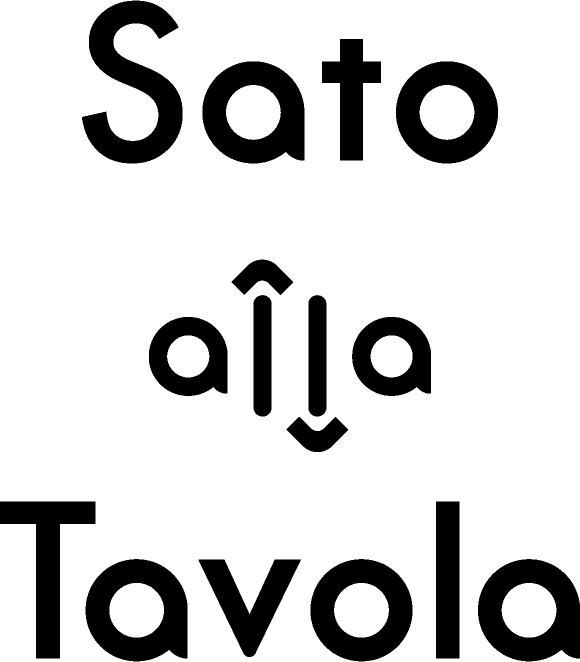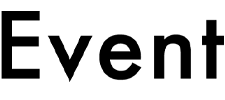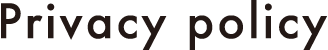“あるを尽くして”共に楽しむ食卓 2024.09.12 開催

“あるを尽くして”共に楽しむ食卓 2024.09.12 開催
さとタボラがプロデュースする、食卓を囲むイベントも第3回目を迎えました。去る9月12日、「800°DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA 日本1号店」にて、長野県小海町の食材を楽しむ「夏の白菜と燻製チョウザメ ”あるを尽くして”生産者と共に町を味わう会」を開催しました。“あるを尽くして”は信州の言葉で、「食べ物を残さない」という意味と「今ある力を出し尽くして」という意味を持ち、外から来た人をあたたかくもてなす信州人のもてなしの心を表わす言葉とも言われます。

長野県の東部、八ヶ岳連峰を南西に望む長野県小海町は、標高が高く寒冷な山間の地。この地域で採れる白菜、レタス、ブロッコリーなどは高原野菜と呼ばれ、これら夏の葉物野菜の生産量は全国トップ。また、高原ならでは澄んだ空気や風土により、希少な「鞍掛豆」や「ハクレイ茸」も作られています。町内には、チョウザメの養殖に乗り出す企業も。そんな、おいしい食材とユニークなストーリーの宝庫である小海町をテーマに、ひとときの夜会が始まりました。

乾杯の前の時間に、さとタボラチームから小海町をご紹介。スクリーンには、小海町の美しい景色が映し出され、テーブルに置かれたオリジナルブックも眺めながら、小海町の風景に思いを馳せる会場の皆さん。この日は、都内や関東近隣、長野県内から様々なお客様にお越しいただきました。そして、小海町から、高原野菜やチョウザメなどの生産にを手がける5名のつくり手、総勢30名ほどの方と共に食卓を囲みました。

この日のお料理は前菜からドルチェまで計6品。最初の一品は、美しい前菜3種の盛り合わせ。ナスやインゲン、キタアカリなどのお馴染みの野菜が、イタリアンのエッセンスが加わって、思わず写真に収めたくなる、目にも楽しい一皿に。メニュー名は、左から、「キタアカリのピンチョス 大王イワナとやまなかの野沢菜」、「ピッツェリアのおやき ナスのマルゲリータ風」、「インゲンと生ハムのムース 青のりとアサリのジュで」。

今回、小海町から駆けつけてくださった農家さんの一人、小池浩二さんは白菜やミニトマトを手がけています。「農家の生態ってあまり想像がつかないと思いますが」と前置きしつつ、長野県の高原エリアでの農家のいとなみについて、しばし語っていただきました。冬場はマイナス20度にもなるため、畑に出ることはできないこと。そのため1年の売り上げをほぼ半年で稼がなければならないこと。早い人は5月中旬頃から収穫をし始め、10月下旬まで休みが1日もないこと。「今日はどうにかやりくりして、ここに来ることができました。明日の朝3時か4時頃にはまた畑に出ていると思いますが…」小池さんのそんな一言に会場は少しどよめき、どこからともなく「ヒュー」という歓声と拍手が。
※高原野菜についての取材レポートはこちらを参照↓「真夏のスーパーに並ぶ白菜の舞台裏」

梅雨の雨をたっぷりと受けて育った夏から秋にかけての白菜は、特有の瑞々しさを持つと言います。また、夏場の1日の寒暖差により葉肉の中に甘みも凝縮。そんなこの時期特有の白菜のおいしさを楽しむオリジナルドリンクが、このイベントのために開発されました。その名も「高原から届いたフレッシュ白菜のサワー」。サトウキビシロップと共にスムージーにして凍らせ、ソルベにした瑞々しい白菜を、酒粕焼酎をベースにサワーとかき混ぜながら味わうという一品です。添えられたミントがフレッシュさを増幅させ、メロンを彷彿とさせる爽やかな香りが一気に喉を潤す一杯は大好評。新たな白菜のおいしさを、つくり手の皆さんと共に楽しみました。

農業を始めて6年目、レッドキャベツや白菜、レタスを手がける小池禎一さんは、「とにかくおいしいもの、自分が食べたいものを作るというのがモットーです」と話してくれました。他のお客様から夢は何ですか?と聞かれると、「小海町の農家みんながまとまって何か全く新しい野菜など、小海ブランドを掲げられるものを作りたいなと思っています」。

「夏のブロッコリーは甘みが強いんですよ」と話す平出明彦さん。農業がシーズンオフになる1年の半分は看護師として働いている奥様と共に農家を営んでいます。お二人のモットーは「半医半商」。「健康に一番大事なのは、口から入るもの」と言う奥様の言葉を大切に、栄養価の高いブロッコリーで皆さんの健康の一助になりたい、と語ってくださいました。

さて、小海町には、チョウザメの養殖に乗り出すユニークな企業があります。※チョウザメ養殖についての取材レポートはこちらを参照↓「ロマンの古代魚にかける夢」キャビアのイメージが強いチョウザメですが、魚肉もとても栄養価が高く、フグと鯛を掛け合わせたような食感、非常に強い旨みを持つ秀逸な食材。成魚になるまで3年もかかるチョウザメ。しかも1匹に対してとれる肉の量はごく少量なため、お肉の方が流通することは滅多にないのですが、今回は小海の高原野菜とチョザメの肉が奇跡的なコラボレーションを果たしました。メインの「チョウザメのスモークと高原野菜のピッツァ」は、サッパリして力強い食感が特徴のチョウザメのおいしさを、燻製することによってが更に引き出し、レタスやブロッコリー、ミニトマトなどの小海のフレッシュなお野菜と絶妙なハーモニーを成す一品。

もう一つのメインディッシュ、「白菜とラルドで包んだチョウザメのバロティーヌ」は、フレッシュな白菜を破ると、チョウザメの驚くほどの旨味が弾ける一品。チョウザメで出汁をとったスープでいただきます。

数々の“小海づくし”のお料理に、舌鼓を打ちながら、この日の会も終盤に。さとタボラチームの一員として小海町現地も取材し、メニューを開発を担当した深澤シェフの「小海町の素晴らしさを食を通して皆さんに伝えられて嬉しい」という感無量のコメントで、会は幕を閉じました。

小海町で早朝に収穫された高原野菜が華やかなテーブルで主役を張り、まちと里の人々が同じテーブルに座り、共に料理を味わって小海町に思いを馳せ、心を繋ぎ合わせたひとときとなりました。