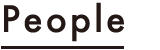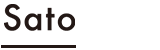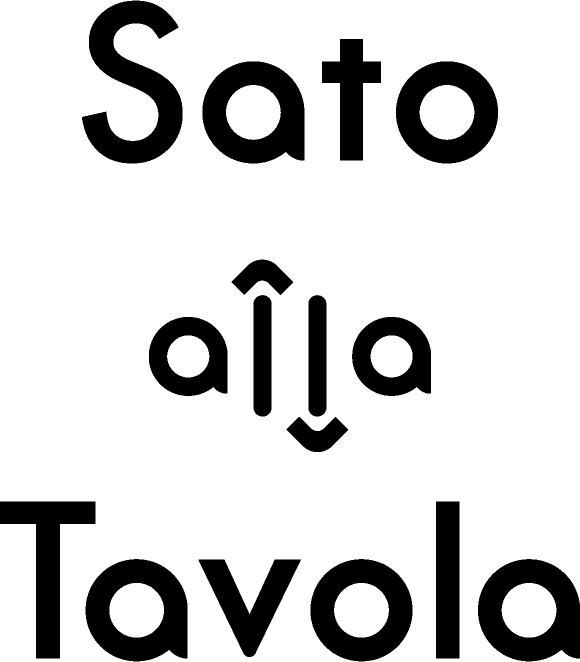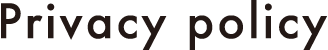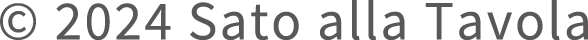おいしいものと、楽しい人と 茨城県大子町視察ノート(4)
2025.04.23


おいしいものと、楽しい人と 茨城県大子町視察ノート(4)
2025.04.23
【地鶏の最高傑作、奥久慈しゃもの生産現場へ】
比内鶏と並んで「地鶏の最高傑作」と言われる奥久慈しゃも。大子町を代表する食材の一つで、さとタボラでもぜひ持ち帰ってメニューに生かしたいところ。そんな奥久慈しゃもの生産者、長山律子さんに会いに行ってきました。視察チームは、大子町の中央エリア、上岡へ。風通しの良い鶏舎に、心地よい音量でラジオがかかっていました。

(写真:日当たりと風通しの良い長山さんの鶏舎。ご両親が建てた豚小屋を改修したもの)
この日、ちょうど生産組合から、孵化したての雛約300羽が届けられるとのこと。視察チームが到着してまもなく、ちょうど雛たちも車に乗ってやってきました。うとうと、よちよちと可愛い雛たち。これから4~5ヶ月の飼育期間を経て出荷されます。これは実に、一般的な養鶏の3倍以上の飼育期間。これまで長山さんの育てた中で、大きいものでは雄鶏で3kgほどの大きさにまで成長したそうです。

(写真:孵化して1日目の、奥久慈しゃもの雛たち。)
長山さんが養鶏を始められたのは、20年以上も前のこと。新聞で、お子さんの空手教室の先生が生産者募集の広告を出しているのを見たのがきっかけ。ご両親が敷地内に建てた豚小屋が余っていたのでそれを改修して飼育を始めました。鶏糞と交換で町内の米農家さんから籾殻をもらい、それを敷き料にしています。そのためか匂いはほとんどなく、日当たりも風通しも良好な飼育小屋で、雛たちも心なしか楽しそうに見えます。

(写真:長山さんと、長山さんの肩に乗るしゃもの雛)
悩みは、夏場熱くて鶏たちの食欲が減退すること。今年は飼料に唐辛子を混ぜて胃腸を活発にする方法などを試してみるそうです。また、鶏は突然の大きな音に敏感で、雷などの音でパニックになり寄り集まって圧死してしまうことも。ラジオがかかっているのは鶏たちを安心させるためなのだそうです。

(写真:「1日餌は朝に一回やるだけだから」と、午前中はお弁当屋さんも兼業しているという、バイタリティ溢れる長山さん)
雛を届けに来た生産組合の方に伺うと、現在奥久慈しゃも全体で地元需要は2割ほど。8割方は県外で、個人の方は北海道から沖縄まで、飲食店も都心を含め全国幅広い取引先に出荷しています。人気のブランド鶏は、心地よい鶏舎でゆっくりと手塩にかけて育てられていました。

(写真:青い屋根の建物が鶏舎)
「今も生産者募集してますから!」コロナ禍で一時期は販売量が激減したり、その後も飼料の高騰の影響で売値を下げざるを得なかったりと、次から次へと課題も。しかし、奥久慈しゃもがもっと認知されるように盛り上げていきたいという長山さんでした。

【アイデアウーマンのオーナーとの心朗らかになる時間 〜藤田観光りんご園〜】
その後、北上して大子町の浅川というエリアへ。大子町で人気なのは、樹上完熟のりんご狩り。完熟前に収穫されたものよりも甘みが強いと言います。取材時は、りんごの花の蕾が膨らみ、1輪2輪、開花し始めたものも見つけました。これが、りんご産地の南限といわれる大子町の4月上旬です。

(写真:藤田観光りんご園。枝の蕾は膨らみ始めている)
藤田観光りんご園の中には、カフェが併設されており、視察チームが到着すると、オーナーの藤田史子さんがちょうど一仕事を終えて戻って来られるところでした。「作業に飽きたとこだったから、ちょうど良かった!」。あっけらかんとした語り口から、冗談がポンポン飛び出します。

(写真:ご主人と共に藤田観光りんご園を切り盛りしている藤田文子さん)
藤田さんは、この地に嫁いで25年。元々倉庫だったという2階建ての建物を改修して、りんご狩りに来る人が休憩したり、食事やバーベキューをしたりできるテラス付きのカフェをつくりました。ここには、観光客だけでなく、地元の方も定期的に集うそうです。1Fには、20年ほど前から「ちょこちょこやっている」という藤田さんが手がけたりんごの加工品がずらり。ジュース、ジャム、ビール、ブランデー、果実をセミドライにしたもののチョコレートがけ、そして、「茨城おみやげ大賞」の金賞を受賞したアップルパイ。大ぶりにカットされた樹上完熟のりんごがゴロゴロ入っている絶品です。

(写真:藤田さんの手がける、りんごを加工したドリンクの数々)
「6次産業化ってハッとする言葉ですが、これからの時代、やって当たり前のことだと自分に言い聞かせています。農家として生き残っていくためには、廃棄や不作も考えて、加工や2次利用も頭に入れてやっていかなければと。若くして就農された方とも、よくそんな話をしています」。これからの時代の農家は、加工や流通、販売までを意識しなければならないと考える藤田さん。摘果したものや自然落果したもの、廃棄されてしまう余った完熟りんごを生かして、長くおいしく提供したい。藤田さんの思いとアイデアの結晶が店頭にいきいきと並んでいました。

(写真:剪定したりんごの枝)
摘果したものを料理に活かせないか、果実だけでなく、剪定した枝を燻製用に使えないか、さとタボラの視察チームとも、いろいろなアイデアが飛び交いました。

(写真:カフェスペースで楽しく歓談。藤田さんのおいしいコーヒーをいただきました。)
4月以降に降りる遅霜(おそじも)の対策として、りんご園の中には、茶畑でも見かけた大きな扇風機が等間隔で設えられていました。

(写真:藤田観光りんご園を上空から)
盆地でありながら標高が高く、山の斜面から冷気が流れ込むため1日の寒暖差が非常に大きいことが大子町の特徴ですが、その寒暖差があることで、果実がますます甘くなるのだそうです。そんな南限のりんご生産現場は、自然の恵みと藤田さんの人柄と思いで、人が集い、新しいアイデアとおいしいものが生まれ続ける場所でした。

(写真:「せっかくなので」と藤田さんと記念写真を一枚)
【丁寧に手ですくい上げられるおいしさ 〜ゆばの里〜】
次の日視察チームが向かったのは、大子町を代表するもう一つの特産である湯葉の生産現場、「ゆばの里」です。この日は、特別に湯葉すくい体験をさせていただきました。衛生白衣を着て加工場に入ると、大豆のいい香りに一瞬で身を包まれます。

(写真:湯葉の加工場。湯気の立つ豆乳)
細長く大きな浴槽のようなものが何列か並び、中に入っている豆乳から湯気がたちのぼっています。格子状の枠の中から1枚の湯葉を引き上げるという湯葉すくい体験にシェフが挑戦。枠に沿ってナイフを慎重に動かし、ぐるりと一周させて湯葉を切り離し、細い棒で洗濯物のようにすくいあげます。さすがシェフ、お上手です。

(写真:初めての湯葉すくいに挑戦するさとタボラのシェフ)
すくい上げた後は少し冷やしてから別の台に移され、切ったり包んだりという作業が続きます。無事に終わってホッとしながらふと隣の列を見ると、一連の作業をわずか2秒?3秒?でこなし続ける、鮮やかすぎる熟練の方の手捌きに見入ってしまいました。

(写真:鮮やかな熟練の技)
すくい上げたばかりの湯葉を、刺身醤油で。滑らかな舌触りと濃厚な大豆の香りとコクが絶品です。「ゆばの里」の湯葉の原料である大豆は、茨城県産「里のほほえみ」など、契約農家の方が丹精込めてつくったもの。水は、八溝山系の地下水を。豆腐づくりで欠かせないにがりには、伊豆大島のきれいな海からとった「海水にがり」を使用しています。

(写真:刺身醤油でいただく生湯葉)
ゆばの里では、こだわりの湯葉を始めとして、さまざまな大豆製品を販売しています。豆腐ソフトクリームも絶品。良い水と素材と、一枚一枚丁寧に手ですくい上げられたおいしさを感じた「ゆばの里」でした。

【一番おいしいと思うビールをつくり続けたい 〜大子ブルワリー〜】
ご当地ビールは、旅の醍醐味の一つかもしれません。大子町に来たら必ず飲んで欲しいのが、「やみぞ森林のビール」。本場ドイツの製法にこだわりぬいた本格クラフトビールです。生産を手がけるのは「大子ブルワリー」。大子町の上金沢というエリアにあり、工場にレストランが併設された、地ビールレストラン。クラフトビールなだけに、ここでいただく生は格別です。

(写真:ガラス越しに醸造所が見学でき、レストランも併設された大子ブルワリー)
オーナーの綿引賢治さんも、やはり「生がおすすめ」とのこと。綿引さんのお話を伺うと、その理由がよくわかりました。大量生産のビール場合は、生きた酵母を機械で完全に取り除いてしまいますが、自然にできたものをそのままお客様に提供するというのがドイツ式クラフトビールの理念。酵母を取り除くのも全て手作業なので、生きた酵母は当然多少ビールの中に残ります。特にヴァイツェンはオリがある方がフレッシュでおいしいと言われますが、長期低温熟成のピルスナーは、自然に酵母を取り除いて透き通ったものがおいしいと言われ、種類によっても異なりいます。ただ、生きた酵母が入っている以上は空気にふれると劣化してしまうもの。樽は全く空気にふれないために鮮度が保たれます。現地で樽から飲む生ビールが絶品なのはそういうわけなのですね。

(写真:オーナーの綿引賢治さん)
ところで、綿引さんのビールづくりへのこだわりは、ドイツ式の製造方法を徹底すること。ドイツにはビール純粋令という古い法律があり、ビールは、麦芽、ホップ、水、酵母の4素材のみを原料とすると定められています。りんごなど、大子の他の素材を掛け合わせた発泡酒づくりにも挑戦しようか、と考えたことも一度だけあったという綿引さんですが(その後別の酒造免許が必要ということを知り、頓挫して笑い話に)、ご自身が飲んで一番おいしいと思うのが、やはりこのドイツ式クラフトビール。醸造をつかさどるドイツ人のマイスター(技術者)を現地から呼び寄せ、大子に7年間住んでもらい、ビールづくりのノウハウを授かったというこだわりようです。

(写真:大子ブルワリーの醸造所内。ピルスナー、ヴァイツェン、へレス、季節限定シーズンビール用の4種類のタンクが並ぶ)
ドイツ人マイスターの職人気質に応えたのは、大子の清冽な湧水。年間を通して水温・水質ともに安定した、ビールづくりにぴったりの大子の湧水から、「やみぞ森林のビール」のおいしさは生まれました。日本の大手メーカーのビールは喉越しが命、キンキンに冷やして飲むのが主流ですが、クラフトビールは麦芽やホップの味が濃いため、常温で飲んで味や風味を楽しむのが欧米の主流。ドイツ式クラフトビールは「味」もおいしい、と綿引さん。お昼にこの大子ブルワリーのレストランでランチをいただいた視察チームも、生ビールの麦とホップのおいしさを十分堪能できました!

【大子町と久慈川をこよなく愛する釣りの名手】
取材チームが旅の最後にお会いしたのは、大子町屈指の釣りの達人、中野一徳さん。町内では「いっとくさん」の愛称で親しまれています。大子町生まれ、大子町育ち。元大子町特産品流通公社の職員で、特産や生産者のお話を伺えば、知らないことはないというほど、町の生き字引のような方です。しかしお話を伺っていると釣りの方がむしろ本業なのではないかと思うほどの釣り好き。大量に鮎を釣り上げてはご近所を集めて振る舞ったりもよくします。そんな中野さんが子供の頃から慣れ親しんだ久慈川の魅力を伺いました。

(写真:中野一徳さん)
中野さんにお会いしたのは、久慈川と、支流・押川が交わるひらけた川辺。中野さんが長くお住まいだったという土地がすぐ目の前の対岸に。現在は家具店が建っているのですが、そのお店と堤防の間、文字通り川の目と鼻の先に、中野さんのお父様が建てたお家があったそうです。お父様も釣り好き。釣り人にとっては一等地です。「朝、釣りやって仕事に行って、夜もまた釣りやって」。思い立ったら30秒で釣りに出られるロケーション。

(写真:久慈川本流)
子供時代もここでよく遊んでいました。「夏はよく向こうの岩の方まで泳いでいましたね。鮎、山女魚、岩魚、鯉、鰻、なまず、いろいろな魚が獲れて。冬にはシガも見られて」。久慈川には、「氷花(しが)」という幻想的な冬の顔もあります。厳しい冷え込みで、水面の温度が0度以下になる時、川底の石の表面の氷がシャーベット状のかたまりとなって水面に浮かび、大きな花びらのように川面を流れるという現象です。昔は川が凍ることもあったそう。「川の端っこにできた大きな水たまりが凍って、スケートをしてよく遊んでました」と中野さん。

しかし、年々多くなる水害で、かつてのご自宅は2回も水没し、3回目はさすがに厳しいということで、河川改修の立退を機に町内の別の場所に引っ越しました。町の最盛期には、この辺りに8階建てのホテルがあり、ボーリング場もありましたが、その頃から人口は3分の一ほどに。川辺の形や風景もずいぶん変わりましたが、「川底の地盤は変わらず昔のままなので、今も夏場は、ここが私たちの遊び場です」と中野さん。

(写真:中野さんの車は釣具がいっぱい。移動式の秘密基地のようでした)
中野さんは、「川を1日見ていても飽きない」と言います。自称「魚目」と言って、流れている川の中にいる魚の姿もよく見えるそうです。「あゆが跳ねる音と山女魚が跳ねる音は違うんだよ」。川面を眺める中野さんの目はキラキラ。それは、獲物を探す釣りの名手の目でもあり、ただこの川が大好きな少年の目のようでもありました。

中野さんの素敵な言葉の数々に癒された旅の最後。視察チームは後ろ髪を引かれるように町を後にしたのでした。今回の旅で得た持ちきれないほどの良い素材とストーリーを次のテーブルにどう生かすか、チームはすぐに作戦を練り始めています。
次回イベントの情報はNewsから。